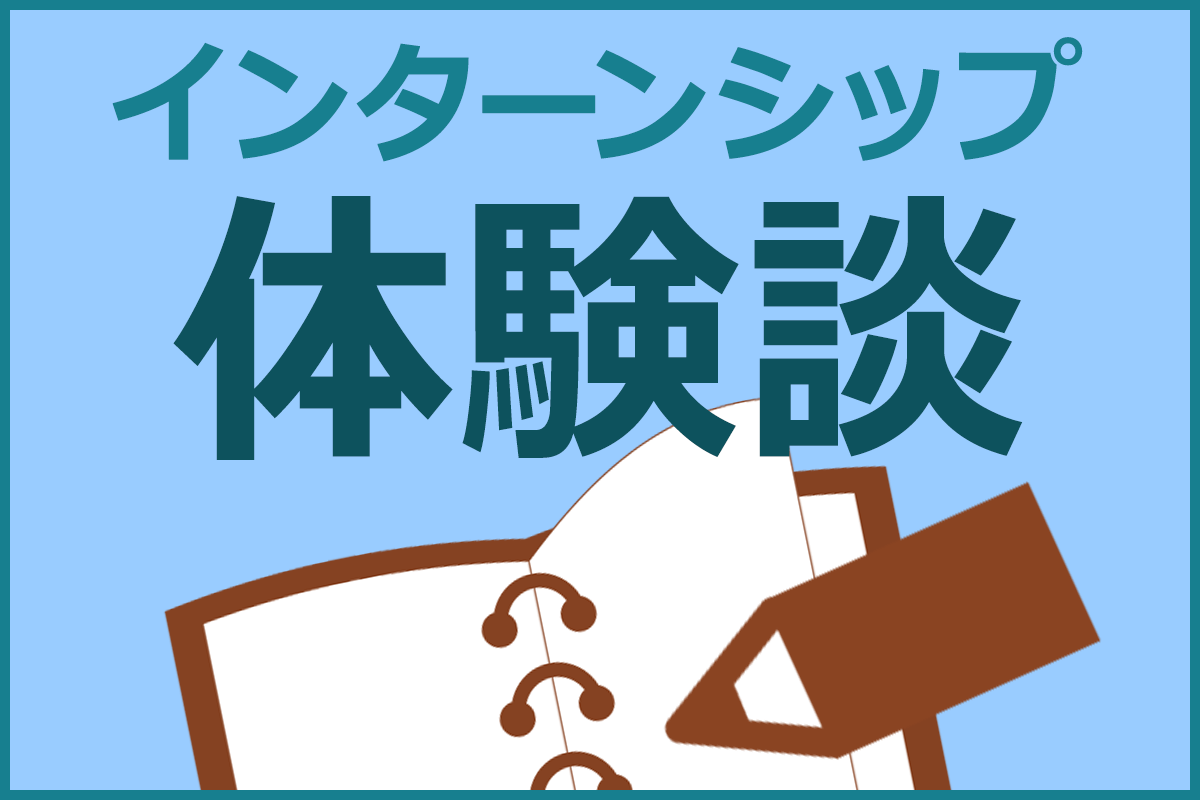日本電産の短期インターンシップ体験談です。
短期インターンシップへの参加を検討している学生は、ぜひ参考にしてみてください!
インターンシップ体験談一覧
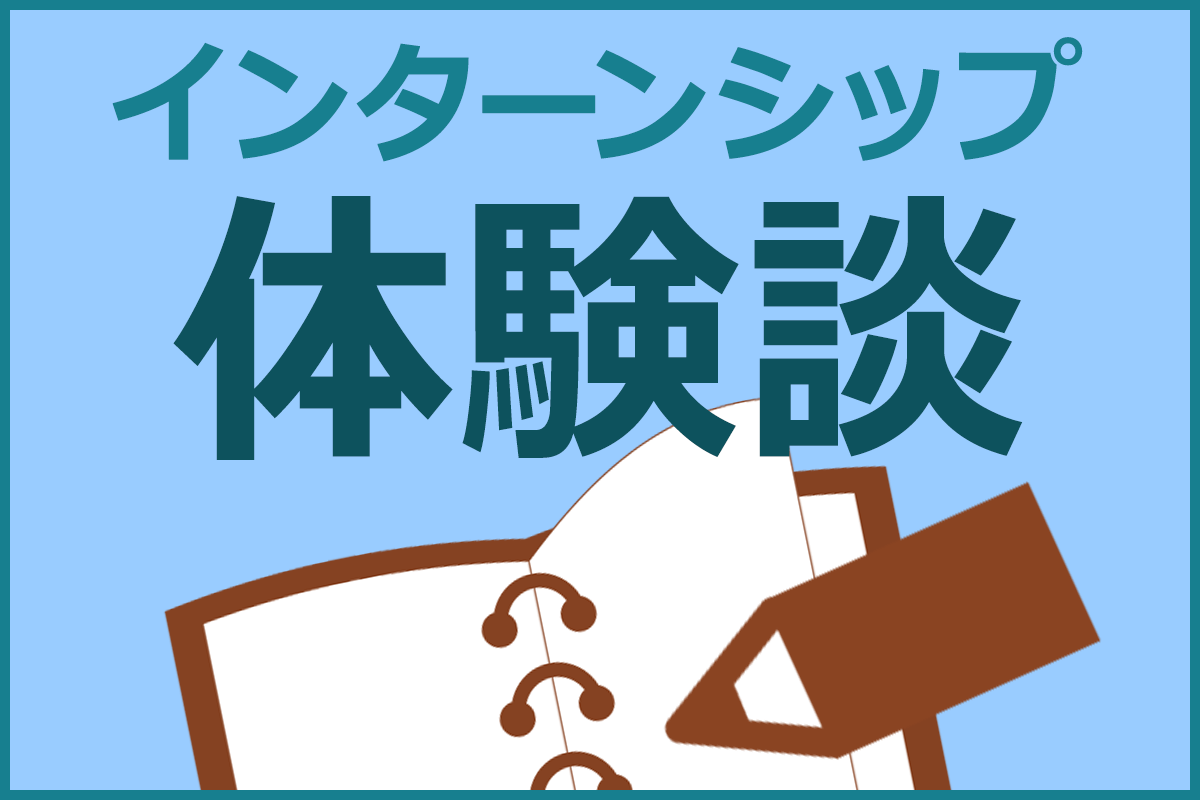
目次
- ・日本電産のインターンシップ(2021卒,12月)体験談
- ├インターン、学生情報
- ├インターンシップに参加した理由、きっかけ
- ├インターンシップ参加のための選考や参加に向けて準備したこと
- ├ES、面接の内容
- ├インターンシップで体験した仕事内容
- ├インターンシップで得たものや成長できた点
- ├インターンシップの報酬
- ├インターンシップ参加後の現在興味のあるor就職予定の仕事、その理由について
- ├このインターンはどんな学生にオススメ?
- └インターンシップに関する後輩へのアドバイス等
- ・日本電産のインターンシップ(2020卒,10月)体験談
- ├インターン、学生情報
- ├インターンシップに参加した理由、きっかけ
- ├インターンシップ参加のための選考や参加に向けて準備したこと
- ├ES、面接の内容
- ├インターンシップで体験した仕事内容
- ├インターンシップで得たものや成長できた点
- ├インターンシップの報酬
- ├インターンシップ参加後の現在興味のあるor就職予定の仕事、その理由について
- ├このインターンはどんな学生にオススメ?
- └インターンシップに関する後輩へのアドバイス等
日本電産のインターンシップ(2021卒,12月)体験談
インターン、学生情報
| 企業名 |
日本電産 |
| インターンシップ名 |
課題解決型インターンシップ |
| 参加期間 |
4日 |
| 参加時期 |
修士1年生の12月 |
| 職種 |
技術職 |
| 卒業予定年 |
2021年 |
インターンシップに参加した理由、きっかけ
インターンシップ自体に興味があったので、ものづくり業界で社会に身を置くことで、自分の実力や自分の研究で身につけた課題解決への考え方を、インターンシップにおいてどのくらい発揮できるかを知りたいと思った。また、自分とは異なる様々な分野の研究をしてきた学生と考え方を共有し、身に付けたいと思った。課題解決型ということもあり、身に付けつつ発表などでアウトプットすることで、スキルアップすることを目標として取り組もうと思った。
インターンシップ参加のための選考や参加に向けて準備したこと
事前に渡される勉強資料があったので、よく読んでいた。また、モーターや日本電産の製品についても調べていった。
ES、面接の内容
以下ESの内容
・志望動機300文字
・学びたいこと250文字
・興味があることや科目300文字
以下質問内容
ESが基本。照らし合せる感じ。
・アルバイト経験
・志望動機
・研究内容
・興味があること
・学びたいこと
・自己PR
また、どんな研究室かや、日本電産のことどこで知ったかなども聞かれた。あまり深堀はされなかった。
インターンシップで体験した仕事内容
課題:班ごとに設定した目標に向けたモーターの作製と評価
(雰囲気や作業の進め方は学生実験みたいに進められる)
班:学部が分散するようにグループ分けされた。
行程
1日目 研究所見学、このとき先輩社員に質問や製品についての質問時間がある。オリエンテーション、名前覚えることと、班目標の設定の時間。次の日のモーター作成に向けて座学。
2日目 与えられたことをやるだけの簡単ワーク。モーターの作製方法を、手を動かして学ぶため。
3日目 班ごとに仕様をきめて、理論計算し、そのモーターを作製。そのモーターを評価し、理論値とのギャップや、仕様のモーターになっているかなどの検証。最終日に向けた発表資料も作成。
4日目 資料訂正と社員の前で発表。
全体の流れとして、座学、作製、評価、考察のローテーションで、わからないことは技術の社員に聞く。
配布資料はあるので、モーターについての知識を手を動かしながら、蓄えていく。
インターンシップで得たものや成長できた点
インターンシップを通して、大きく変わったことはない。ただ、技術的な面では事前に渡される勉強資料があり、補足資料や本も配られるので、モーターの知識はしっかりつく。しかし、資料不備が多かったり、座学もいい加減なところが多かった。ワークを通して、社員交流が少ないため、進め方も自由なのであまり社会人を感じられない。専門外だと非常に難しく、電気的な知識ばかり使うので、他学部だと負担が大きかったり、ついていけなくなるので、成長はしにくい。
インターンシップの報酬
一日500円
インターンシップ参加後の現在興味のあるor就職予定の仕事、その理由について
半導体業界。確かにモノ作りが楽しいことを実感したが、自分の研究が活かせる分野に行きたいと思った。また、この企業は座談会で社員が自分自身に自信がなさそうで、仕事をやらされている感が否めない。ここは採用人数が多く、自分がやりたい仕事内容ができない雰囲気が漂う。会社に求めるものではないが、懇親会などもなく、少し暗い感じがした。
このインターンはどんな学生にオススメ?
ものづくりや学生実験が好きな学生
インターンシップに関する後輩へのアドバイス等
モノ作りや学生実験が好きな学生にはお勧めできるが、時間や課題のレベル的にハイレベルでの議論ができず、また求めているような社員からのフィードバックは得られない。モノ作りを楽しみたい人や、モーターを知りたい人にはお勧めできるが、社会人としての働き方は不透明で、この会社で働くイメージは想像しにくい。課題のレベルがあまり高くないので、インターンシップが初めての人には非常に参加しやすい。また、早期選考の案内もあるので悪くはない。
会員限定コンテンツです。
これより先をお読みになる場合には会員登録/ログインが必要です。
日本電産のインターンシップ(2020卒,10月)体験談
インターン、学生情報
| 企業名 |
日本電産株式会社 |
| インターンシップ名 |
講演会・面接対策インターンシップ |
| 参加期間 |
1日間 |
| 参加時期 |
大学3年生の10月 |
| 職種 |
総合職 |
| 大学名、学部名 |
立命館大学 産業社会学部 |
| 卒業予定年 |
2020年 |
インターンシップに参加した理由、きっかけ
電機メーカーに興味を持った理由は、BtoB向けのビジネスに大きな関心があったからです。私は、趣味でエキストラをやっており、そこで裏方の重要性というのを強く感じ、様々な業種の企業活動を裏から支えるBtoBの会社に大きな関心を持ちました。そこで、大企業であり、BtoB向けのビジネスも大規模に行っている日本電産について、深く学びたいと思い、参加を決めました。また、面接に不安を抱えていたので、面接対策もしたいと思い、それも参加の決め手となりました。
インターンシップ参加のための選考や参加に向けて準備したこと
企業のHPを見ました。
ES、面接の内容
本インターンシップでは、事前に選考がなく、
エントリーした人から先着順で参加者が選ばれました。よって、選考における特徴やポイントは特にありませんでした。このインターンシップは、選考がないものの、電機メーカーについて学べるだけでなく、面接のコツも学べるので、良いインターンシップだと思いました。
インターンシップで体験した仕事内容
本インターンシップは、日本電産株式会社についてよく知るということに加え、日本電産に限らず、就職活動における面接全般に役立てることができる面接のコツを学ぶというコンセプトのもと行われました。全体として、グループワークはなく、講義中心でした。会場は京都にある日本電産のオフィスビル内のホールで、参加学生は30名ほど、社員さんは2名ほどいました。具体的なプログラムの内容としては、最初に社員さんによる電機メーカーの業界と日本電産について、基本的な概要や近年の動向などの解説がありました。次に、管理職(部長クラス)の方が登壇し、管理職から見た今の日本電産についてや、新入社員に期待することなどの話をされました。最後に、面接対策として、実際に日本電産が使っている面接評価シートなどを用いて、どんなポイントで学生を評価しているか、どんな学生が面接を通過できるのかについて解説がありました。全体的に、解説が丁寧で分かりやすく、資料も多くいただけたので、理解を深めることができました。
インターンシップで得たものや成長できた点
本インターンシップで学んだことは、「学びつつげることの大切さ」です。これは、管理職の方がお話されていたことで、ビジネスパーソンになったからといって、与えられら仕事をするだけでいいのではなく、自発的に様々なことを学び、スキルを上げ、キャリアップして行ったり、会社としての成長を促したりしていくことが大切であると学びました。その管理職の方は、仕事が終わっても、何時間も主体的に学んでいたということで、私も語学や社会情勢など、自分にとって何を学ぶべきかをしっかり分析し、学び続けていきたいと思いました。
インターンシップの報酬
なし
インターンシップ参加後の現在興味のあるor就職予定の仕事、その理由について
就職予定の業界は通信業界です。私は、大きな災害を経験したことがあり、それ以来、生活インフラを支える会社に勤め、人々に安心・安全で快適な生活環境を提供したいという思いを強く持っていました。その中で、変化が大きく、成長業界でもある通信業界に就職を決めました。
このインターンはどんな学生にオススメ?
電機メーカーや面接対策に関心がある学生。
インターンシップに関する後輩へのアドバイス等
業界や企業を無理に絞り込むのではなく、少しでも自分の興味がある業界や企業のインターンは幅広く参加し、自分のキャリアの視野を広げることが大事だと思います。特に社員の生の声が対面で聞けること、実際に仕事を疑似的でもいいので体験できること、選考につながる(つながりそうな)ことの3点を基準にインターンを選ぶことをお勧めします。また、インターンシップのエントリーシートでは、具体的な独自性のあるエピソードを盛り込んだ上で、その経験がインターンシップの志望理由とどうマッチするのかを論理的に書くことを意識してほしいと思います。さらに、このインターンシップのように、面接について学ぶためにインターンシップを活用するというのも有効な手段だと思うので、ぜひこのような機会を積極的に利用してほしいと思います。
会員限定コンテンツです。
これより先をお読みになる場合には会員登録/ログインが必要です。