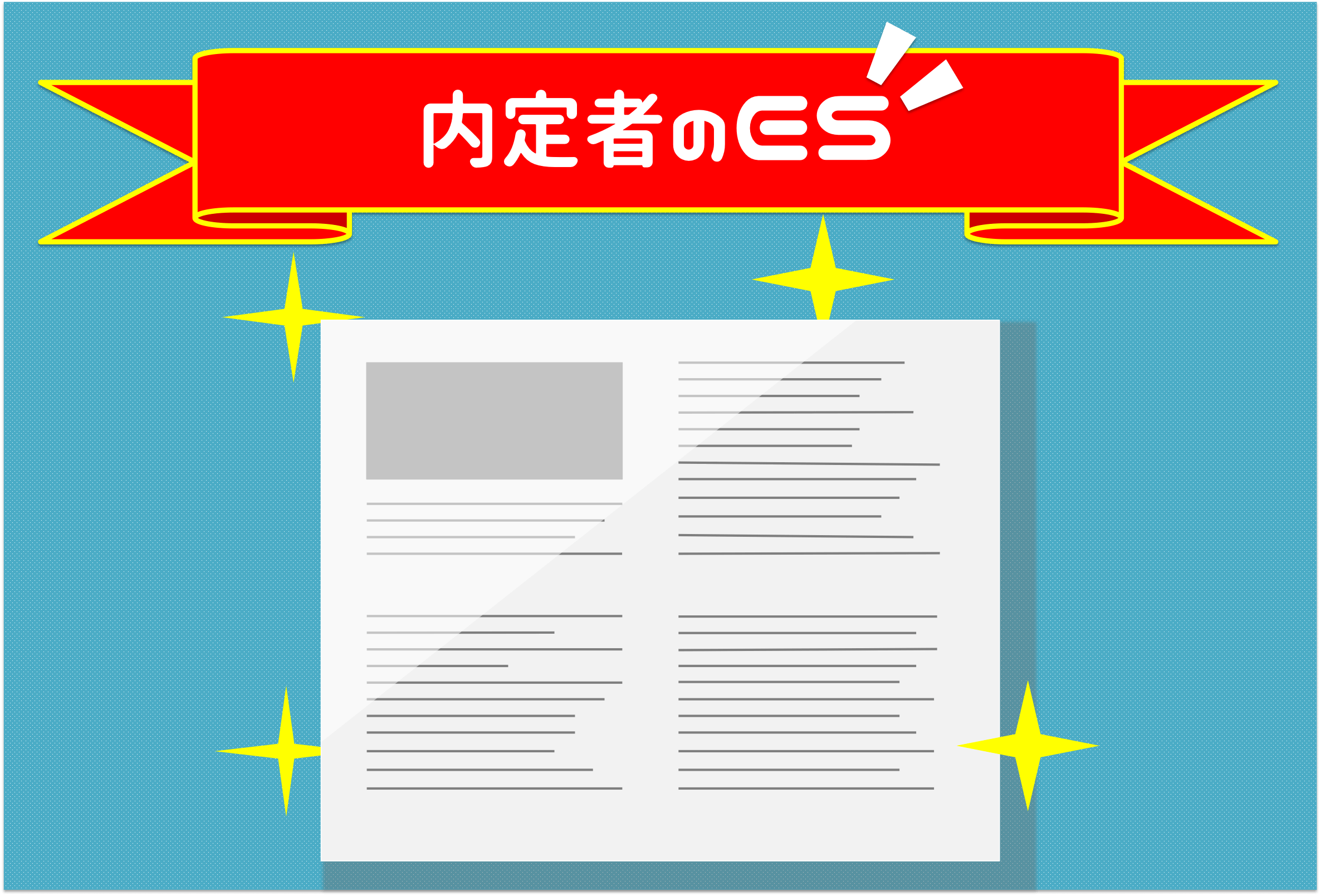内定者のエントリーシート&選考レポートを参考に、内定を勝ち取りましょう!
ESに加え選考フロー、選考アドバイスも見ることができます!
内定者のES一覧
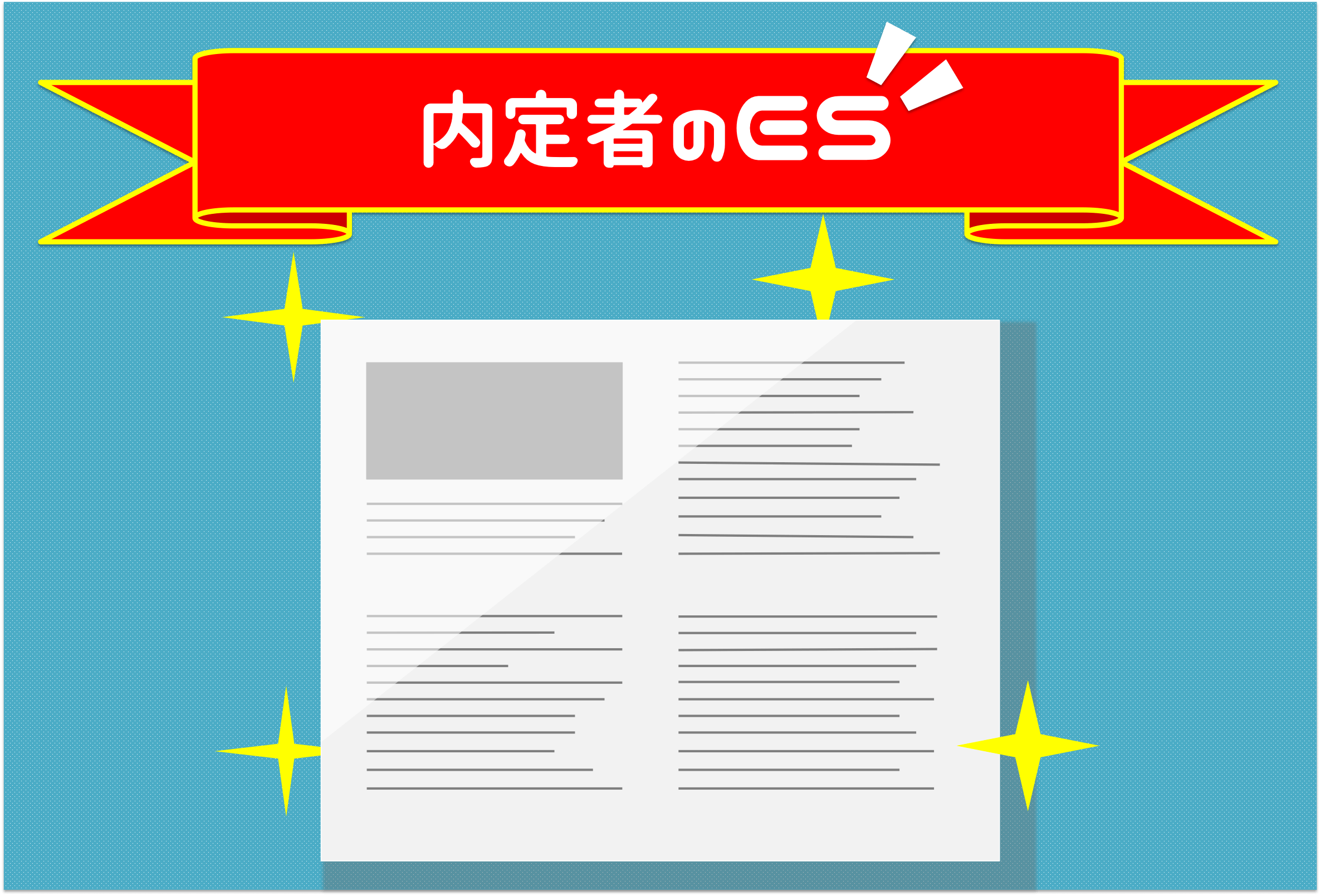
本田技研工業 2021卒,総合職内定者エントリーシート
A-1:学生生活において、もっとも力を入れて取り組んだ学問・研究テーマは何ですか。
翼面上のシートキャビティの界面捕獲を考慮したキャビテーションモデルに関する研究
また、その内容について具体的に入力してください。500
流体機械設計時のコスト低減や、安全面の保証精度向上を目的として、キャビテーションの数値シミュレーションに関する研究をしています。
キャビテーションは、液相中における圧力低下によって、気泡が発生する現象であり、気泡破裂の衝撃から、流体機械の部品を壊してしまうこともあります。
そのため、安全に製品の設計をするためには、流体機械にかかる力などの正確な解析を行うことでキャビテーションの発生を許容内に抑えることが重要です。
特にコスト面・安全面からシミュレーションによる解析が期待されます。
しかし、これまでのシミュレーションでは、流体機械の解析のもととなる最も基本的な翼周りの解析でさえ、キャビテーション形状や翼にかかる力を正確に予測することはできていません。
多くの計算モデルでは液相と気相を区別せず、均質な流体としてキャビテーションを表現していたことが原因の一つでした。
そこで私は、キャビテーション発生時に気相と液相の界面を正確にとらえることで予測精度を上げ、流体機械の安全設計に貢献することを目的として研究をしています。現在は気相と液相の界面を一次関数で近似することで界面を考慮したモデルを構築しています。
A-2:その学問・研究テーマにどのように取り組み、何を得ましたか。300
私は主体性を重視して研究に取り組み、自ら課題を見つけ、解決する重要性を学びました。
私は卒業論文提出の二か月ほど前にプログラムコードの大幅な変更を試みました。
自分の研究で捉えたい現象を再現するためには大幅な変更が必須だと考えたためです。
指導教員からは時間の関係で勧められませんでしたが、私は指導教員に自分の考えを説明し、納得してもらいました。自ら考えた課題であったため、解決する道筋もスムーズに立てることができ、卒業論文提出までに、自分が捉えたい現象を再現することができました。
自ら見つけた課題に対しては、責任感が生じ、解決方法も考えやすいため、仕事をするうえでも非常に重要なことを得られたと感じます。
B-1:学生時代に最も情熱を注いで取り組んだ内容について入力してください。200
関西学生マジックショー出場を目標に自分の鳩マジックを組み上げたことです。
私は大学入学時に、新しいことにチャレンジしたいと考え、マジックサークルに所属し、鳩マジックを練習しました。
また、入部当初にマジックの勉強のために見に行った関西学生マジックショーにおいて、たった数分で多くの人を喜ばせるステージマジシャンの魅力に衝撃を受け、自分の鳩マジックでショーに出演し、多くの人を喜ばせるという決意をしました。
B-2:取り組みの過程で直面した困難なことは何ですか。また、その困難を乗り越えるために「どうしたか」を、自身の想いなども踏まえて入力してください。500
テクニックの上達具合が頭打ちになってしまったことです。
どれほど練習を重ねても、自分の器用さや、マジックに割けられる時間を考えると、人を感動させるほどのテクニックを身に着けるのは難しいことを悟りました。
そこで私は技術ではなく、
見せ方や間の取り方を重視してマジックの手順を組むことにしました。
マジックショーでは如何に不思議に、派手に、美しく見せるかが大事であると考えたからです。
私は20本以上のマジックの動画を見て観客が大きく反応するところを分析しました。さらに先輩やOBなど、できるだけ多くの人からアドバイスをもらって観客を楽しませる方法を考えました。
それをもとに、私は鳩を手に乗せたときに美しく羽ばたくように粘り強く調教したり、鳩の絵が描かれた額縁の紙を突き破って鳩を出すなど、オリジナリティのある派手な現象を多く考えました。さらに派手な現象の前には溜めを作ることや、曲の最も盛り上がる所で一番見せたい現象を合わせる手順にすることで技術が高くなくても人を楽しませることができる演技にしました。
その結果、ショーへの選考を突破し、その発表会で会場を大いに盛り上げ、観客アンケートでは3位に選ばれました。
B-3:その経験から何を学びましたか。それをどのように仕事に活かしていきたいですか。300
人が何を求めているか、どうしたら人が喜ぶかを考える大切さを学びました。
私は本当の目標を理解することで、その実現手法が技術を磨くこと以外にもあることに気づきました。それが突破口となり、目標に近づくことが出来ました。仕事をする際にもこの考え方を持ち続けたいと思います。
仕事において、私は自分が作った製品で人を喜ばせたいという夢があります。
マジックの経験から学んだことを活かし、どうしたら人が喜ぶかを、お客様の立場で深く考えたいと思います。そして自分が携わる製品の個別の技術にとらわれず、人を喜ばせるという目標を常に考え、人が求めるものを満たす方法を柔軟に見つけることで達成したいと思います。
C-1:あなたが仕事を通じて成し遂げたいことは何ですか。500 その根底にある想いや理由をあわせて入力してください。
私はニーズ以上の価値を持つ製品を開発し、多くの人を驚かせ、喜ばせたいです。
私は鳩マジックで多くの人を喜ばせた経験から、仕事でも人を喜ばせることでやりがいを感じたいと思いました。
さらにエンジニアとして人を喜ばせるには、製品に対してニーズ以上の価値を持たせることが大切だと感じています。実際、私は追加の機能に驚き、それが嬉しくて商品を買うことが多くあります。
その中でも私が仕事をする際には、人の心を大きく動かせるような製品にこの価値を追加することで感動するほどの喜びを提供したいと考えています。
私自身、心を大きく動かされた経験として、初めてスポーツカーに乗ったことが印象に残っています。想像以上に洗練されたフォルムや強烈な加速に衝撃を受け、一気に車が好きになりました。
車には人の心を大きく動かす力があることを知りました。さらに車には心地よさや楽しさなど、人を喜ばせられる切り口が多くあることからも、車という製品で人を喜ばせたいと感じました。
私は、車として人が想像する以上の快適さや格好良さを実現する、または考えたことのないような新しい価値を追加することで、人が驚き、喜ぶ車を設計したいです。
C-2:実現の場としてHondaを志望する理由を入力してください。300
貴社の腹を割って話し合う社風が人を喜ばせる製品を作れる環境だと思ったからです。
私は研究活動で指導員に自らの考えを話し、納得してもらったことで結果を出せた経験から、腹を割って本気で話し合うことの大切さを知りました。
貴社ではボトムアップ形式で社員全員がより良い車を作る提案をし、会議では身分や年齢に関係なく意見をぶつけ合うということを聞きました。これは利益を追い求めるよりも質のいい車を作るという目標から、社員全員が強い思いや自分の意見に対する責任を持って仕事をしているからだと感じました。そのような環境であれば人を喜ばせられる車づくりができると考え、貴社を志望します。
D:これまでの入力内容に加えて、伝えたいことがあれば自由に入力してください。200
私は人のためになることなら努力を惜しまない性格です。
塾や家庭教師のアルバイトをしていた際には教え子が志望校に合格するように指導時間外でも自分でオリジナルの問題を作って解かせました。
その際には志望校の過去問を数年分読み込み、分析することで傾向を把握しました。教え子が合格した際にはとても喜ばれ、私もとても嬉しかったです。
この性格は、貴社で働く際に一生持ち続けられる原動力となると思います。
内定者プロフィール
| 会社名 | 本田技研工業株式会社 |
|---|
| 学校名 | 大阪大学 |
|---|
| 学部系統 | 工学部 |
|---|
| 職種 | 総合職 |
|---|
| 卒業年度 | 2021年 |
|---|
| 内定日 | 1996年6月29日 |
|---|
選考フロー
ES,webテスト→一次面談→最終面談
面接、ES作成にあたり頑張ったこと、工夫した事
長いESだが、なので自分の考えを一貫して書くことを心掛けた。
HONDAでないといけない理由を深く書いた。
就活生へのアドバイス
なぜトヨタではなくHONDAなのかをしっかりと答えられるようにするといいと思います。
面談では、逆質問をいっぱい考えておいたほうがいいと思います。
会員限定コンテンツです。
これより先をお読みになる場合には会員登録/ログインが必要です。
本田技研工業 2021卒,技術系(自動運転コース)内定者エントリーシート
A-1学生生活において最も力を入れて取り組んだ研究テーマについて
<テーマ名>(100)
<内容>(500)
<テーマ名>(100)
〇〇と〇〇に基づく〇〇の構築と〇〇を用いて〇〇を促進する〇〇システム開発
<内容>(500)
〇〇では、〇〇には〇〇と〇〇の差分の認知が重要であるとされています。それを基に、〇〇は〇〇によって決定されるという仮説を立て、〇〇をキーワードとして〇〇を構築するとともに〇〇に有効な方策を検証しています。実験ツールは〇〇を用いた〇〇です。〇〇の〇〇には〇〇、〇〇のモデル、〇〇が反映されます。また、〇〇を再現するために、〇〇同様の〇〇を設置しました。実験では参加者が〇〇等の〇〇が必要とされるタスクを行います。この時、〇〇などの〇〇指標に加え、〇〇などの〇〇指標が併せて計測されます。これらのデータと〇〇から、〇〇を構築します。最終的には、〇〇についてのデータが〇〇で計測され、リアルタイムで〇〇を評価して即時的に〇〇する〇〇システムを開発します。
A-2その研究テーマにどのように取り組み,何を得たか?(300)
〇〇の90%以上が〇〇であるという報告があります。そのため〇〇によって〇〇を向上させる試みが多く為されてきています。しかし、根本的に〇〇を改善させて〇〇を実現させることも必要であり、さらには〇〇を通じて〇〇にも繋げられるのではないかと考え、本研究テーマを選びました。実験の結果、〇〇と〇〇で比較した場合、〇〇と〇〇の間には有意な相関があることがわかり、〇〇を数理モデル化することができる可能性が示されました。今後はこの結果を基に、〇〇による〇〇システムを構築し、その有効性を検証していきます。
B-1:学生時代に最も情熱を注いで取り組んだ内容について入力してください(200)
私は小学生の頃から〇〇としても注力してきた〇〇に最も情熱を持って取り組んできました。私は学部生時代、〇〇を体育会にて極めたいと思う反面、〇〇以外でも多様な経験を積みたいとの好奇心もあり、〇〇同好会を軸に活動しました。本同好会の主な取り組み内容は〇〇と週末に組まれる練習試合であり、夏と冬の年2回開催される〇〇の大会での優勝を最大の目標としていました。
B-2:取り組みの過程で直面した困難なことは何ですか。また、その困難を乗り越えるために「どうしたか」を、自身の想いなども踏まえて入力してください(500)
本同好会は〇〇への熱意も個人力も高いメンバーが多いものの、私が入部してからの2年間は〇〇の大会で良くてベスト8という成績までしか残せず、より高みを目指すためには〇〇が必要だと考えました。〇〇が不在のチームであるが故に〇〇を見ながら〇〇を練る視点が欠けていた為、
日々の練習も〇〇に欠ける状況があり、私は如何にすれば〇〇を高められるかという点に着眼しました。そこで私は〇〇を自ら中心となって導入し、〇〇を客観的に分析していく事で〇〇のみならず〇〇を試みました。苦心したのは、〇〇方法です。〇〇をチームメートと共有する際、特に先輩方にとっては下級生から〇〇ばかりを一方的に伝えられると、たとえ指摘が正しいとしても素直に聞いてもらえないと考えました。そこで私は丁寧かつ適切な〇〇、〇〇と〇〇を合わせてお伝えすること、〇〇をとって互いの〇〇を無くすことを心掛けました。その結果、〇〇を得て〇〇する事に成功し、3年次の〇〇の大会で優勝するに至りました。
B-3:その経験から何を学びましたか。それをどのように仕事に活かしていきたいですか?(300)
この経験を通じて、〇〇のように〇〇する人物がいない環境でも、〇〇を共有し、〇〇を重ねれば良い結果を出せることを学びました。また、〇〇での分析手法を導入するまでは、〇〇するのを無意識のうちに怠っていたことに気づきました。私は本同好会での経験が〇〇の現場でも非常に重要だと考えています。なぜなら、〇〇では〇〇を導くためにチーム内で考えて〇〇しながら進めていく場面が多いと私は考えているからです。貴社に入社後は、一つ一つの〇〇に対して常に〇〇を持ち、〇〇しながら〇〇を重ねて〇〇を導き出せるような人になりたいと考えています。
C-1:あなたが仕事を通じて成し遂げたいことは何ですか。その根底にある想いや理由をあわせて入力してください。(500)
私は〇〇ができ、かつ全ての人々の〇〇に合う〇〇された〇〇を作りたいと思っています。〇〇に携わる人の使命の一つは、〇〇を限りなくゼロに近づけることだと思います。そのため、〇〇の開発は、〇〇できない人や〇〇が充実していない地域で生活する上で嫌でも〇〇しなければならない人の〇〇に資するほか、今後少子高齢化で労働人口が減少する日本の〇〇を支えるために絶対に必要な取り組みです。一方で、私のように〇〇することが趣味である人たちの〇〇を〇〇によって奪いたくないとも思っています。また、人が〇〇を保持することは、〇〇システムの機能不全時における〇〇として重要であるだけでなく、〇〇を通じた〇〇の繰り返しにより〇〇させることにも繋がると考えています。ゆえに私は、〇〇できることを念頭に置いた上で、利用者の〇〇に応じて〇〇・〇〇というように臨機応変に〇〇を切り替えられるような〇〇を作り上げたいと思っています。
C-2:実現の場としてHondaを志望する理由を入力してください。(300)
理由は2つあります。1つ目は〇〇に手加減をしない姿勢です。貴社のインターンシップでは、〇〇を恐れず、むしろ本気で〇〇するところに強く〇〇しました。ゆえに、今までにない新しい〇〇に〇〇したいという私の希望を貴社で実現したいと思いました。2つ目は〇〇に囚われないで〇〇からいい〇〇を作ろうとする姿勢です。競争の激しい〇〇において、〇〇に選ばれ続けるためには、その〇〇にしかない価値を生み出すことが重要だと思っています。私も貴社の一員となって、お客様が「〇〇」と思えるような価値を提供する〇〇をしたいと考えています。
D:これまでの入力内容に加えて、伝えたいことがあれば自由に入力してください。(200)
私はインドへの一人旅で途方に暮れる事件に次々と遭遇しました。渡航前にあらゆる状況に対応出来るよう備えたつもりでしたが、タクシーに乗っても違う場所に連れていかれるなど、自分の知識や経験だけでは対処出来ない場面が多いことを痛感しました。そこで積極的に現地の方々に助けを求め、同方向に向かう現地の方を探し出し同乗してもらうことで解決していきました。この旅を通じて得た様々な経験は人生の宝物になっています。
内定者プロフィール
| 会社名 | 本田技研工業株式会社 |
|---|
| 学校名 | 筑波大学 |
|---|
| 学部系統 | システム情報工学研究科 |
|---|
| 職種 | 技術系(自動運転コース) |
|---|
| 卒業年度 | 2021年 |
|---|
| 内定日 | 2020年6月5日 |
|---|
選考フロー
エントリーシート・WEBテスト→マッチング面談→最終面接
面接、ES作成にあたり頑張ったこと、工夫した事
ESは文字数がとても多いので,制限文字数を考えずに書いた.
面接では誠実な態度で臨んだ.
就活生へのアドバイス
ESを書くのが非常に大変なので,ネタとなるエピソードを考えておくと良い.
会員限定コンテンツです。
これより先をお読みになる場合には会員登録/ログインが必要です。
本田技研工業 2019卒,総合職内定者エントリーシート
「学生時代に最も情熱を注いで取り組んだ内容について入力してください」(500字)
ゼミでのグループ論文執筆活動に情熱を注いで取り組んだ。そこで私は論文のまとめ担当という役割を担った。私は誰でもユニークな意見を遠慮せずに言える環境を作る為に、明るく和気藹々とした空間を作るよう行動した。例えば会議室で議論するのではなく、ゼミ員の自宅で飲んだり食べたりしながらカジュアルに話し合いをすることで、意外なアイデアが生まれることがあった。勿論、発表前の資料作り等では静かで集中出来る環境で作業する等、メリハリをつけて作業をした。そして論文のテーマは「◯◯」だった。一般的な◯◯研究は豊富だったが、◯◯に特化した研究はなかった。この未知のテーマに対する答えを見つけたいという想いで、ゼミ員と協力しながら、商業に関する新聞・雑誌記事などの文献を70年分以上読み、また実際に施設に赴いて価格やテナント構成を調査し、裏付けを行った。この論文を完成させた経験は、仲間と自由に意見をぶつけ合いながら、一つの目標の為に努力したという点で私の大切な財産であると考えている。
「取り組みの過程で直面した困難なことはなんですか?」(500字)
論文の作成にあたって直面した困難は2つあった。1つ目はゼミ員の論文執筆に対するモチベーションがバラバラだったということである。私の所属するゼミでは12人で一つの論文を作成するのだが、中にはサークルやバイトが忙しい人もいて、
全員が論文に全力で取り組める環境とは言えなかった。このように全員の意思統一がされず、各個人でモチベーションに差があるために全体の進捗の遅れが発生した。またモチベーションの低い人が他人に作業を任せきり、作業量が偏ることで不平等感が生まれ、ゼミ員同士のわだかまりを生んでしまう可能性があった。2つ目は個人の得意分野に差があったことである。◯人もメンバーがいることで、数的処理が得意な人、文章力がある人、アイデアを出す力がある人、資料をまとめる能力のある人など、専門性に優れている人が多くいた。しかしその半面、ある作業に対して一人に頼りきってしまい、その人が休んでしまうと全体の作業が止まってしまうという問題が発生した。
「困難を乗り越えるために「どうしたか」を、自身の想いなども踏まえて入力してください」(500字)
私は「誰一人仲間外れになることなく、全員が納得して気持ち良く、楽しく論文を作る」という想いで行動した。1つ目の困難に対しては、私が一人一人とコミュニケーションを取り、なるべく無理のないスケジュールを作るように協力した。またモチベーションが低い人に対しては、あえて低い人同士でグループを作らせ、自分がやらなければいけないという責任感を持たせることにした。そして作業が終わった後にはゼミ員同士で食事や散歩をしながらコミュニケーションを重ね、心理的な距離を縮めることで、全体の意思統一を図った。2つ目の困難に対しては、一人が同じタスクをずっと続けるのではなく、担当する章や役割をローテーションさせるようにした。これによって知識を全体で共有し、一人一人が様々な能力を養うことが出来、誰かが休んでも全体の進捗に影響しないようになった。またゼミ員同士のコミュニケーションが盛んになったことで、専門的な知識がある人が積極的に他の人に教える風土ができ、誰か一人に頼って不平等感が生まれることを防げた。これらの努力の結果、全員が納得して楽しく作業をするという目標が達成出来た。
内定者プロフィール
| 会社名 | 本田技研工業株式会社 |
|---|
| 学校名 | 同志社大学 |
|---|
| 学部系統 | 経済学部 |
|---|
| 職種 | 総合職 |
|---|
| 卒業年度 | 2019年 |
|---|
| 内定日 | 2019年5月29日 |
|---|
選考フロー
ES・筆記→GD→面接
面接、ES作成にあたり頑張ったこと、工夫した事
簡潔に。結論ファースト。
就活生へのアドバイス
数多ある自動車メーカーの中で、何故ホンダが良いのかを言語化すること。
会員限定コンテンツです。
これより先をお読みになる場合には会員登録/ログインが必要です。