就活の選考で多くの企業が実施しているグループディスカッション(GD)・グループワーク(GW)。
「なぜか受からない」「落ちる理由がわからない」「何が評価されているのかわからなくて対策ができていない」という就活生も多いのではないでしょうか?落ちる人にはどんな特徴があるのでしょう?
今回は、グループディスカッションがうまくいかない原因や落ちる人の特徴、グループディスカッション対策などについて解説します。
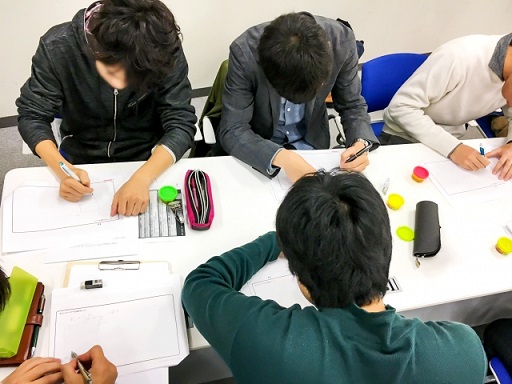
- ・グループディスカッションがうまくいかない原因
- ├時間配分がうまくいかなかった
- └ゴールの共有がうまくできておらず、最後に意見がまとまらなかった
- ・グループディスカッションで落ちる人の特徴
- ├自分の意見を話すことに時間を使い過ぎてしまった
- ├アイデア出しの段階で否定的な発言を多くしてしまった
- ├周りが先に進んでいってしまい、うまく議論に参加できなかった
- └周りがよく喋り過ぎて自分が話すタイミングを掴めなかった
- ・グループディスカッションで見られているもの
- ├グループディスカッションで評価されるポイントとは
- └グループディスカッションで評価される行動・振る舞い
- ・グループディスカッションでは決まった役割、役職に就くべき?
- ├大事なのは役割よりも「貢献度」
- └自分の力を発揮できる役割につくことが重要
- ・「グループディスカッション対策」で自信をつけよう
- ├普段から自分の意見を持つことを習慣づける
- ├友達とグループディスカッションの練習をしてみる
- └インターンで場数を踏んでグループディスカッションの雰囲気に慣れる
- ・最後に
グループディスカッションがうまくいかない原因
グループディスカッションで落ちる原因でよくあるのが、個人の失敗ではなくチームとしてグループディスカッションで失敗してしまうというケースです。よくある事例と対策をみていきましょう。
時間配分がうまくいかなかった
(事例)
与えられた時間が短いため時間配分を決めることに時間を割くのはもったいなく感じ、一気に進めていけば時間内に終わるだろうと考えて進めてしまった。
その結果、うまく結論がまとまる前に時間が終わってしまった。最後の発表がボロボロで、グループのメンバー全員落ちてしまった。
(対策)
時間内に結論までたどり着くということはグループディスカッションで最も大事なことです。
議論が始まってしまうとどうしても時間を意識できなくなってしまったり、自分が時間を意識していてもメンバーに意識できていない人が居て細かい話を始めてしまったりします。大まかでも良いので、時間配分は最初に決めるようにしましょう。
もちろん、最初の時間配分通りにはいかないこともあります。それでも、いつまでにどの段階まで進んでいれば良いかを最初に仮決めしておけば軌道修正もスムーズに行うことができ、適切な時間配分で結論までたどり着くことができます。
ゴールの共有がうまくできておらず、最後に意見がまとまらなかった
(事例)
チームで1つの答えを出さなければならなかったが、メンバーによって目指すゴールが異なっていたことが最後の最後に発覚し、話がまとまらなかった。
(対策)
グループディスカッションやグループワークでは、チームとして1つの答えを出さなければいけません。
例えば、「売上を伸ばせ」の場合だと長期的売上か短期的売上かでとるべき施策が大きく異なります。最終的な目的について捉え方が人によって異なる可能性がある場合は、なるべく早い段階でチーム内での認識合わせを行いましょう。
また、課題の中に解釈の幅があるような言葉が出てきた場合も、チーム内での認識合わせを行なっておくべきです。
グループディスカッションで落ちる人の特徴
ここでは、グループディスカッションで落ちる人の特徴を挙げています。なかなか選考を通過できないという学生は、自分が以下のどれかに該当してしまっていないか、振り返ってみましょう。
自分の意見を話すことに時間を使い過ぎてしまった
(事例)
グループディスカッションの序盤のアイデアを出し合っていく段階で、アイデアがたくさん思い浮かんだので、それを思いついた順に全て話していたら時間を使い過ぎてしまい、ほかの学生がアイデアを話す時間を奪ってしまった。
(対策)
アイディアは思いついた順に話すのでなく、自分の中である程度まとめてから話す癖をつけましょう。
グループディスカッションでは限られた時間というリソースを効率よく使って結論に導かなければならないので、良いことを言っても時間を使いすぎたらマイナス評価です。
あらかじめ決めた時間配分から1人あたりの使える時間を計算して、それをグループのメンバーと共有しておくと良いでしょう。
アイデア出しの段階で否定的な発言を多くしてしまった
(事例)
アイデア出しの段階で他人の意見を否定し過ぎてしまい、誰もアイデアを話そうとしなくなってしまった。
(対策)
たとえ自分と違う意見を言っている人が居たとしても、すぐに否定するのは得策ではありません。否定する場合は、相手の意見の良い部分についても言及するなど、柔らかい言い方を心がけましょう。
また、アイディアをとりあえずブレインストーミング方式で出し切ってから吟味していく、というような進め方で議論を進めているのにアイデア出しの段階で否定してしまうのはマナー違反です。
正論を言うことももちろん大事ですが、「一緒に働きたくない」と思われるような振る舞いをしてはいけません。他人の意見を否定するときは、慎重になりましょう。
周りが先に進んでいってしまい、うまく議論に参加できなかった
(事例)
周りの議論のスピードが速く自分の理解が追いついたころには、他のメンバーがもう別の内容について話していて完全に取り残されてしまった。
(対策)
グループディスカッションは、チームで進めていくものです。他の人の話でよくわからないことがあったときは遠慮なく、「それはなぜですか?」や「それってこういう認識で合っていますか?」と聞きましょう。
わからない時に質問してメンバー内での認識を共有するということは仕事をする上でも大事なことですので、質問することは場合によってはプラス評価にもなります。
周りがよく喋り過ぎて自分が話すタイミングを掴めなかった
(事例)
よく喋る学生ばかりのグループになって、自分が話し始める前に他の人が話してしまい、ほとんど発言できなかった。
(対策)
就活では誰もが評価されるために必死ですので早口でたくさん喋ってしまいがちですが、そういうメンバーに囲まれてしまった時は別の部分でアピールする手もあります。
例えば、「話をしている人の目を見て相槌を打ちながら話を聞く」というテクニックがあります。人の話をよく聞くというのは好印象ですし、話をしている人も「よく聞いてくれている」と感じるとその相手の方を見て話すようになります。
そうすると、皆の話をよく聞いているだけでだんだん議論の中心人物のような雰囲気を醸し出すようになり、自分が話をするタイミングもつかみやすくなります。
グループディスカッションで見られているもの
グループディスカッションはどんなポイントが評価されるのかわかりにくく、落ちる原因がわからないと言う就活生も多いでしょう。
グループディスカッションで評価されるポイントとは
「積極的に発言をしたほうが良い」と言う人もいれば「発言は少なく、ここぞという時だけすれば良い」と言う人もいて、何が正しいかわかりにくいのがグループディスカッションの難しいところです。企業ごとに評価基準が異なると言うのもまた対策を難しくしています。
ただし、どんなグループディスカッションでも共通する評価基準は、「チームの成果に貢献しているかどうか」です。
グループディスカッションで評価される行動・振る舞い
積極的に発言をして貢献できることもあれば、発言を少なめにしてそのかわりにチームを俯瞰して見ることでここぞと言う時にチームを良い方向に導くというような貢献の仕方もあります。
そのためグループディスカッションでどう振る舞うべきかは一概に語るのが難しいのですが、評価される動き方としては以下のようなものが挙げられます。
・時間配分や結論への議論の道筋を決める
・問題の定義をはっきりさせる
・他人のアイデアをひとまず肯定し、アイディアを出しやすい雰囲気をつくる
・議論を紙にわかりやすくまとめる
グループディスカッションでは決まった役割、役職に就くべき?
ここでは、グループディスカッションでの「役割・役職」について解説します。
大事なのは役割よりも「貢献度」
グループディスカッションではリーダーや書記、タイムキーパーなどの役割を明確に決めて行われたり、明確に決めなくてもそのような動きをする学生がいます。
役割・役職には積極的に就くべきなのでしょうか?また、就くべきだとしたらどの役割が有利なのでしょう?
このような疑問が湧いてきますが、役割に就くこと自体は評価にはあまり関係ありません。大事なのは「チームの成果に貢献しているかどうか」であり、どの役職であるかは本質的には重要ではないのです。
自分の力を発揮できる役割につくことが重要
ただし、決まった役割を持った方が自分の得意なことを活かしてチームに貢献できるというのであれば、積極的に役割を持つのは有効な手です。
リーダーとしてチームをまとめるのが得意であればリーダーを買って出る、紙にまとめるのが得意なら書記を買って出る、といった具合です。
自分がチームの成果に貢献できる振る舞い方が何なのか、というのは何度かグループディスカッションを受けているとだんだん見えてきますので、数をこなすことも大事です。
「グループディスカッション対策」で自信をつけよう
グループディスカッションが苦手な人は、ここで紹介する対策を実践してみてください。
普段から自分の意見を持つことを習慣づける
グループディスカッションの時に「意見が思いつかない」「何を発言していいかわからない」という人は、「考える練習」からはじめてみましょう。
ニュースをみたり新聞を読みながら自分の意見をまとめてみるなど、日常生活の中で自分の意見をまとめる練習をするのも有効です。
友達とグループディスカッションの練習をしてみる
「グループディスカッションのたびに緊張してしまう」「うまくたち振る舞えない」という人は、家族や友人に協力してもらい、グループディスカッションの練習をしてみるのもいいでしょう。
できればグループディスカッションをしている様子を撮影して、後で見返してみてください。自分の態度や話し方を客観的に観察してみると、それまで気づかなかった欠点や問題に気づくことができると思います。
インターンで場数を踏んでグループディスカッションの雰囲気に慣れる
グループディスカッションは、「慣れ」も大切です。インターンシップの面接ではグループディスカッションが導入されていることが多く、インターンの内容もグループディスカッションやグループワークであることが多いです。
1日や数日など短期のインターンプログラムも多数実施されているので、興味のある業界や企業のインターンシップにはできるだけたくさん参加して、グループディスカッションの経験を積んでおくのもいいでしょう。
インターンシップガイド会員登録の特典
厳選インターン情報
短期、長期、学年不問などの全国のインターン募集情報を探せる!
締め切りカレンダー
人気インターン締め切りや就活イベントをカレンダーでチェック!
先輩の体験記
企業毎のインターン体験談や内定者のエントリーシートが読める!
企業からの特別招待
企業から交通費や選考免除等の嬉しい特典の招待が届くことも!
最後に
今回はグループディスカッションで落ちるよくある原因と対策、何が評価されるのかといったことを解説しました。
「個人ではなくチームとして成果を出すことに貢献する」「一緒に働きたくないと思われるような言動は避ける」ということを意識して臨むことが大事です。
慣れも必要ですので、短期インターンなどでグループディスカッションの経験を積んでおいたり、友人と練習しておくということも役立ちます。
グループディスカッションはコツを掴めば通過率が一気に上がるので、しっかり対策しておきましょう。
- 就活イベントまとめ(2016年度) 2025/4/22
- permalink test 2 | 西谷テスト株式会社 2025/4/16
- permalink test | 西谷テスト株式会社 2025/4/16
- test作成 2025/4/1
- 公開テスト | special-testとフリープラン 2025/3/31
- 長期インターンとは?期間・給料・メリットデメリットを解説 | 2025/3/11
- test作成その2 2025/1/22
- 見た目テスト 2025/1/16



